この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です。
今期の主なニュース
国内
色々あった部分はすっ飛ばすとして
エガちゃんねる EGA-CHANNEL “無題”
世代が微妙にズレる上、まさに自分好みの芸風の芸人さんかと言われると特にそういうわけではないのですが、面白いかつまらないかと問われたら、その昔めちゃイケ時代の江頭さんで大笑いさせてもらったことは何度もありました。
「お前に一言モノ申す!」とか「がっぺムカつく!」とか言ってた頃ですね(今でもそうなのかな?)。
と言うことの他、江頭さんってなんだかんだで今時珍しい(?)昔気質の芸人さんなんですよね。
今にして思うと、江頭さんあたりを境にそういう(その人、あるいはそのコンビ・グループ等々の出演自体が楽しみになる、というような)芸人さんめっきり減ったなぁ、なんて思えたりもしますが、それはさておき。
今回、とあるバラエティ番組内での一コマがいわゆるネットイナゴ達(≒あまり質がよろしくない、迷惑系オバサン等の群れ)による被害を被ったようではありますが、既に騒動の相手方の女優さんからも「ネットで騒がれていることは事実とは全く異なる」という趣旨を持つ声明が出されたようで。
イナゴであればまだ佃煮にしたりすることも出来るでしょうが、ネットイナゴなんて存在そのものがただ迷惑なだけで誰の何の役に立っているわけでもない、似ても焼いても食えませんからね。
今更ですが、改めて、猫も杓子もお手軽にネットにアクセスできてしまう昨今。
いい加減、SNSにはもっと実効性を伴う健全な規制が欲しくなるところですね。
それは、やれば面白いのでしょうが
参考:GAME Watch “「龍が如く8外伝」謎多きエンディングの真意は? シリーズチーフディレクター堀井亮佑氏インタビュー。ファン必見の開発裏話もお届け“
インタビューの雰囲気が醸すような好評一辺倒の神作品だったというよりは、特に古くからのユーザーを中心として、賛否の物議を醸した側面もあったように思えた“8外伝”。
強いて言うなら真島の兄さんのファン、あるいは如くシリーズ初見のユーザーに向けた外伝ですね。
世界が突飛だとか何だとか以前に、何でこの作品が龍が如く8の外伝として出されたのでしょうかというあたり。種々のインタビュー記事などを参照してなお未だに強く疑問が残るところではあるのですが、“如く”のタイトルを付さずに売る自信が無かったか、あるいは“外伝”といえば既存のファンを喜ばせるために作られるものだというイメージ定着を嫌ったか。
よくわかりませんが、なんらかの商業戦略的な判断があったりしたのかもしれません(?)。
いずれにしても、意図するところが分かりにくいといえばわかりにくいところではありますね。
そもそも純粋に物語としての突飛さで比較したとしても、同じ龍が如くのスピンオフ作品であるOTEや維新あたりの方がはるかに上ではないかと思いますが(むしろハワイ=海賊という結びつけにはなんとなくチープな安直さを感じるし、どちらかというと平々凡々寄りではあるように思えます)、そういう比較はさておき、シリーズのファンが求めるのは第一には突飛な話ではなく王道の話しではないでしょうか。
一般論としてのその手の挑戦にしても、前作がとっ散らかったままの状態となっているタイミングで次作に求められてしかるべきものなのですかね?
なんてことは思わされました。
エピローグ部分でとりあえずの形に落とされているとはいえ、先が気になる形で終わっている部分なんて、8作中にはそれこそいくらでもあるわけですからね。
モノには順序ってものがあるし、いずれ8外伝をやる機会があるにしても、それは“8”の世界がスッキリしてからの話しだよね、なんて思ってしまったので、今このタイミングでは8外伝のプレイはスルーしました。
関連:龍が如くシリーズ
いわゆる司馬史観の延長で
参考:現代ビジネス “日露戦争の「終盤」を見るとわかる…「明治のリーダー」と「昭和のリーダー」の「決定的なちがい」“
そもそも日露戦争がなぜ開戦に至ったかと言えば、ロシアの南下政策がどうだ、列強の帝国主義がなんだという部分と同様に、時の日本外交も然りだったということもその一因にあがります。
開戦前外交を振り返るにしても、当時の日本が紛争勝利国・戦勝国であり続けたこと、さらに結果として日露戦争に勝利したことから日本史的には不問に付されているような部分も多々ありますが、結局は維新後のスタンダードとなった無茶な日本外交に遠因を持っています。
実際にパワープレイをゴリ押せたのはなぜかと言えば、いわゆる明治維新を境として日本国内の制度・常識が一変することになったからだと考えるのがその場合の筋になって来ますが、「明治素晴らしい!昭和陸軍NG!」という典型的な司馬史観は、結局のところ勝てば官軍負ければ賊軍という、いわゆる明治維新を礼賛する立場に根を持つものです。
一般的にこの史観ベースで日本の近代史が回顧される場合、明治も昭和もただ勇ましさを良しとするような美徳を抱えている点ではあんまり変わらないです、とは絶対にならず、忌憚なく言えば「負けるケンカをする奴が悪い」って理屈で、日清日露は勝てたから賛美する、対米戦には負けたからそれっぽい戦犯レッテルを用意するって方向に進んでいくのが原則です。
作家としての司馬遼太郎さんは自身の経験に基づいた独自の史観を持っていた、そのことが数多の名作の源となって行ったという部分についての安直な批判はどうかと思いますが、だからといってその結果・思想を読み手が自説とする場合についても同様かと言えば、その場合には相応の注意が必要になって来るのではないだろうかとは重ね重ね思います。
“陳腐”の故は無批判の”司馬史観”受け売りにあるのだということですね。
そんな部分からは、まだまだ他にやりようがいくらでもあったような時代(幕末~明治期)に生きた一軍人・大山巌と、ほぼ国の未来も結論も固定されてしまったような時代(明治半ば~昭和初期)に、官僚組織の中でいわば貧乏くじを引かされた内政・外交・軍の最高責任者・東條英機を比較するというやり方自体、いかにも典型的な司馬史観好みの対比で、なんとも恣意的なものを感じさせます。
対比の結果の結論ではなく、”司馬史観の主張”という結論から遡って根拠を拾い集めた類の構成ですね。
昭和陸軍NOと言いながら、石原莞爾のような関東軍のイケイケ天才軍人が全くと言っていいほど叩かれることが無いのは、司馬さんがさほど叩いていないからなのか、それとも東京裁判で起訴されなかったからなのか、東條英機と対立関係にあったからなのか、あるいは何かそれ以外の理由があるのか。
その辺はよくわかりませんが、そのあたりも判で押したようなテンプレ反応と言えばそういうことになりそうですね。
同じ満州国つながりでも、例えば岸信介さんあたりが陰謀論と共にいまでもしつこく叩かれ続けているような嫌いがあることに比べると、石原閣下のそういう部分はなんとも謎な部分でもあります。
ともあれ。
そもそも小御所会議から戊辰戦争終戦までの流れ、士族反乱から西南戦争までの流れ、さらには明治14年政変に続く明治憲法制定や国会開設までの流れがそれを如実に示すように、明治国家が造り上げたパラダイム自体、常に言論弾圧上等・武力行使上等の果てに出来た世界です。
大山巌、あるいは児玉源太郎、山本権兵衛といったいい意味で例外的な薩長人脈中の”人物”をここぞとばかりに引っ張って来ては日露戦争にまつわる事情を礼賛して終わりとなる前に、例えば幕末・維新期の幕臣だった小栗忠順が幕末期にどれだけの仕事をしたかなんて感じのエピソードは引けないものですかね、とも考えてしまいます。
昭和の陸軍の暴走とやらに引っかかったというような体のことを論じる前に、そもそもの始まりであるいわゆる”明治維新”を疑問視する視点は持てないものでしょうか、ってことですね。
ちなみに小栗忠順は経済外交でアメリカと五分に渡りあい、横須賀に製鉄所・造船所を作り、洋式軍隊の制度を確立し、兵庫に日本初の株式会社(兵庫商社)を設立した幕府官僚です。
後の時代に訪れた、文明開化の端緒を付けた人物だともいえるかもしれませんね。
時あたかも、江戸幕府在りし幕末期の話しです。
幕臣がこれだけの仕事を進める能力を持っていた時に、同じ民族内部で血を流してまでわざわざ新しい政府をつくる必要なんて、ある? って話でもありますか。
もっと言うなら、その小栗忠順を含む、新見正興率いる万延年間の遣米使節団と、明治のいわゆる岩倉使節団の違いも大概だったようですが、万延遣米使節が日米修好通商条約の批准書交換のためにアメリカに渡った時、批准書交換と同時に日本に不利なものとなっていた金銀の交換比率を本来あるべきものに改正させたのは、前記した小栗忠順の仕事でした。
使節団はアメリカの民衆にも大歓迎で迎えられるなどまさしくプロの外交使節団としての面目を保ったようですが、後者、すなわち岩倉使節団はそもそも全権委任状を持たずに渡米したため条約改正交渉自体が成立しなかった、当然万延の遣米使節団ほどの注目を浴びたわけでもなかったことを手始めとして、無駄な大所帯で必要以上の期間にわたったことが結果的に”西郷下野”と言う形で内政にも影響を与えることになった等々、そもそも派遣自体に物見遊山的な性質があったことが、しばしば指摘されます。
戊辰戦争期に新政府(薩長藩閥)サイドで大活躍したのが密輸された大量の外国製火器だったこと、維新政府がともすると江戸期以前の日本の歴史を全否定しかねない勢いで欧化を進めたこと等々とも併せれば、尊王攘夷とはいったい何だったのかなんて目線も追加されることになるでしょうが、やがて新政府にとってのラスボスが”維新三傑”の一人である西郷隆盛になろうとは、本人はおろか藩閥の有力者にしても夢にも思わなかったことでしょう。
華族制度を新設した後に四民平等を宣言し(四民の平等とは?)、神道を国策の中心に据えるために仏教を破壊した、そういう人たちが討幕勢力を母体として政府中枢を同郷の身内で固めた上、立ち上げ早々にパトロンを囲い込んで汚職まみれとなって行った、その横で義によって起った東北・北陸諸藩を(密輸火器で)殺戮して作ったのが、いわゆる明治国家です。
こと「汚職まみれ」という点では、三井の番頭さんと揶揄された、鹿鳴館を作って欧化政策を促進した元尊王攘夷派、長州藩出身の井上馨がその代表例ですが、この井上馨の汚職もみ消しに奔走したのが“維新三傑”の一人にカウントされている長州藩・木戸孝允だった、なんてことも言われています。
それは西郷隆盛じゃなくても嫌気がさしてくるところになって来るでしょうが、そのあたりが力こそ正義の国、勝てば官軍の国のはじまりの、本当のところの一側面ですね。
色んな意味で、実に恐ろしい話しです。
「あれは仕方が無かった」「これも仕方が無かった」とは、司馬史観的なモノの見方で維新政府を解釈(≒礼賛)する時にしばしば使いまわされる理屈回しですが、なら討幕無しで江戸幕府が存続していた場合にも日本の国の行く末に全く同じ歴史が用意されていたかと言えば、まずそんなことは絶対になかったでしょう。
架空の前提でタラレバを語っても意味がありませんが、少なくともあり得ない量の焼夷弾で首都圏が丸焼きにされ、長崎広島に原爆が落とされみたいな未来だけは絶対になかったのではないかと思われます。
とどのつまり。
「どうしてこうなった」を考えるのであれば、「その時代にその国を生きた人達がどう振舞った結果どうなった」という個別具体的な部分以前の部分で「その時代のある程度優秀な人であれば、最後にはだれが舵を取ってもそうなることが必然だった」、要は「そういう国として作られたためにそういう国になってしまったのだ」ってことですか。
無理が通って道理が引っ込んだ世界の中、上辺の大山・東條比較で答えが出せるような問題では全く無い、ってことですね。
明治政府がある意味奇跡的に(?)体を為すことが出来たのも、結局はそこに幕末育ちの人材がいたからだ、日本民族にはまだまだ”江戸時代で終わったはずのサムライの魂”が宿っていたからだと考えるとスッキリ筋が通りそうですが、恐らくは明治生まれ、大正生まれの方々(我々のご先祖様)が国を守ることに命を賭してくださったという勇敢な姿勢にしても、素晴らしき明治維新・明治政府様が何を為してくださって云々などでは全く無く、誇り高い”サムライ魂”が隔世遺伝したが故のことなのでしょう。
政府と言う「ハコ」がどうあれ、当時の日本民族・日本社会にはそれだけのポテンシャルがあったのだということですか。
それもこれも、明治国家に連なる現在の日本国において、今日日の日本人の民族性からは完全に消え失せてしまったのではないかと思われる類の、実直な勤勉さであり、高潔な精神あってのことですね。
翻って、国として民族としての歴史の連続性を考える時。
それでも今を生きる日本人は、一体どこに過去とのつながりを求めるべきなのか。
「がっかりさせられる」と知った口を利くは易しですが、中々に難しい問題ですね。
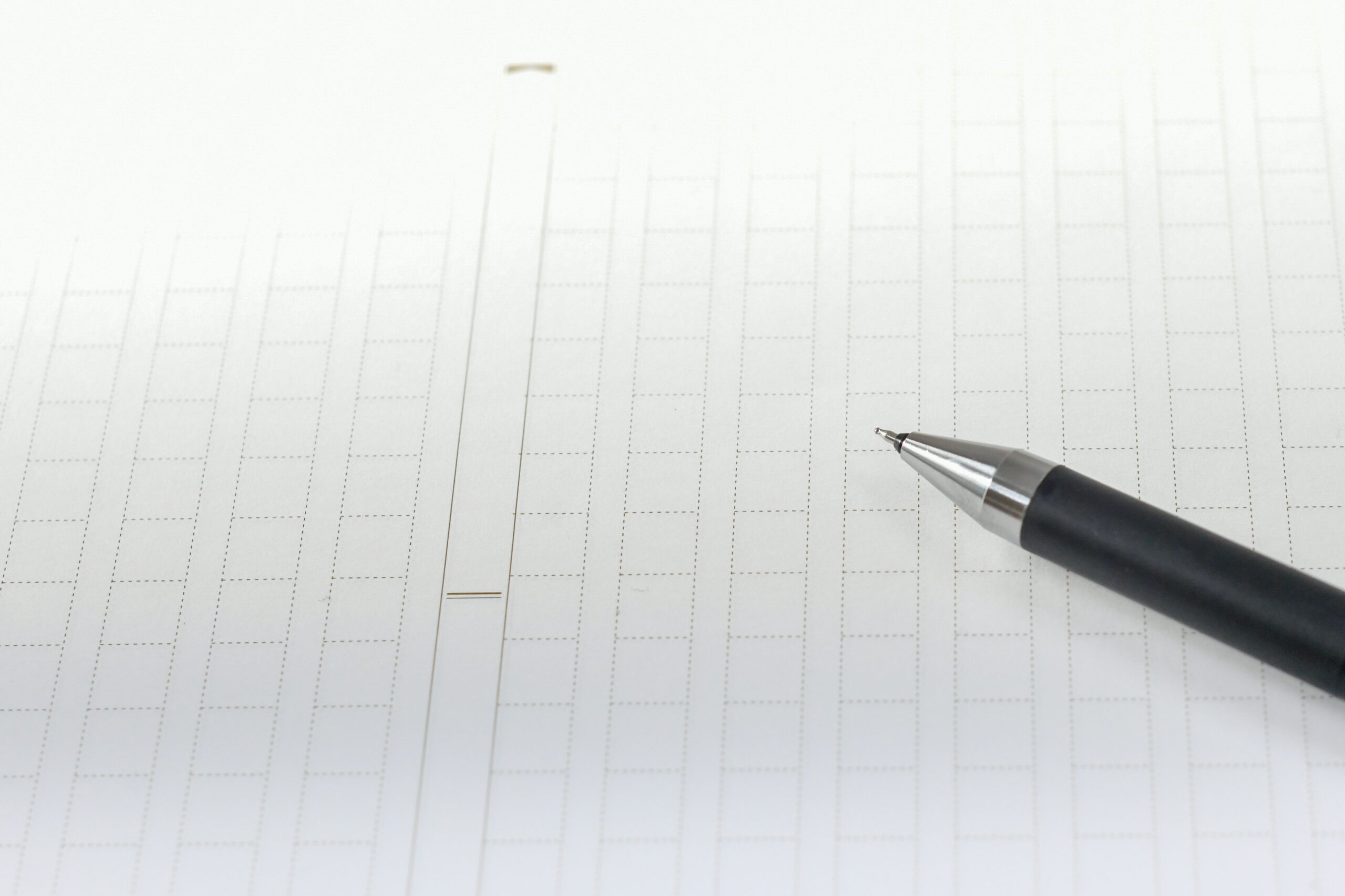


タグ